



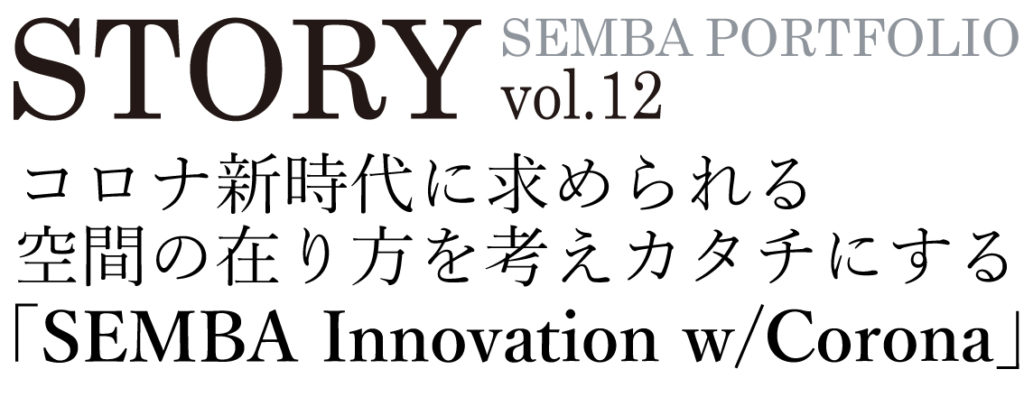
苦境に立つ“お店”のために私たちができること
2020年、私たちの日常を突然襲った、コロナウィルスの猛威。
多くの人が外出自粛を強いられ、買い物や外食、イベント等、他者と接して何かをすることが“これまで通り”とはいかなくなった。
私たちが携わってきた多くの店舗が苦境に立たされる中、店づくりを生業にする私たちに、何かできることはないか…
その思いから立ち上げた「SEMBAInnovationw/Corona(以下SIwCo)」の取り組みと、プロダクト化した2つの製品についてご紹介します。

Project Member / プロジェクトメンバー
-

堀田卓則
株式会社船場
CREATOR事業本部長 執行役員 -

加藤麻希
株式会社船場
エシカルデザイン本部長 執行役員 -

横木忍
株式会社船場
イベント事業本部長
-

本田洋介
株式会社船場
エシカルデザイン本部 re Division -

竹内央
株式会社船場
WEST事業本部 -

荒木勲
株式会社船場
WEST事業本部 -

松田文晶
株式会社船場
イベント事業本部
きっかけは、朝礼での呼びかけ
堀田
最初のきっかけは、コロナ第一波の真っただ中の時に、私がスピーチした5月の全社朝礼でのコメントでした。こんな世になってしまい、この状況を乗り越えるためのアイデアを我々が世に出すことはできないだろうか?と。
加藤
“わたしたち船場全員で”というのが肝でした。普段は事業として空間づくりに取り組んでいますが、SIwCoは自分事として課題にどう向き合うか?「船場社員みんなが、自分事として」という堀田さんの発信に社長が素早く反応し、朝礼後すぐに指示が来たのです。そこで私と堀田さんが中心となりSIwCoを起ち上げました。スピードが絶対でしたので、朝礼での呼びかけから全社公募まで2週間くらいで準備をしました。
最初は20〜30案くらいくればいいかなと思っていたのですが、一気に300案以上集まり、驚きました。毎日この表題のメールが、こちらが追いつめられそうな程の量届いたんです。
堀田
プレゼンテーションを納得のいく形でまとめたい人が多く、「締め切りを超えます!」、「追加でもう1案出します!」などのメールも多く届きました。1人で4案出す人もいましたよ。
走りだしたものの、初めての試みでしたので、社長と社内の人間だけで選考してもいいのか?外部の人にジャッジして貰う方がいいのではないか?など、いろいろ考えました。なぜなら、私たちが気付かない“金の卵”となるアイデアが埋もれてしまう懸念もあったからです。
加藤
海外も含む全社の各支店社員、お客様と通常は接点を持たないバックオフィスの社員、企画書を作ったことがない社員も・・・様々な人がアイデアを送ってくれました。1番最初に届いたのも総務から。ママの目線、主婦の目線、道で並んでる時の視点など、自分がいち利用者として考えた、日常生活に密着したアイデアでした。規定の企画書フォーマットに合わせて、一生懸命まとめてくれて、ちょっと泣けるくらい感動しましたよ。

堀田
海外のローカル社員、台湾やシンガポールからは、英語でハイスペックなアイデアが送られてきました。実現したら面白いよね!って思うような手の込んだものでした。
似た様なアイデアも多く出て来た中で、最終的に選ばれたのは「なにこれ!」と目を引くインパクトのあるもの、そして「面白いんちゃう?」っていうユニークさ、ノリの良いものですね。
加藤
日々提案に慣れている社員は提案書も上手です。あと、デザイナーとして知名度がある人のアイデアにどうしても目が行きがちです。実際に選ばれた竹内さん、荒木さんの提案書もそれぞれ目を引く、味のあるものでした。しかし、選ばれた理由は、利用者目線で「面白い!」と思えたからです。
SIwCo総監督である八嶋社長は内装やデザイン畑ではないので、変な色眼鏡はなしに、提案のひとつひとつを純粋に利用者目線で見て選定し、最終的に選ばれたものにも納得できる要因がありました。
本田
普段我々は内装の設計や施工をやっているので、そこから離れた“製品”としてアイデアを見たとき、とても新鮮に見えました。「そんな細かなことまで考えてるんだ!」など、多くの気づきがありました。300超全てのアイデアを机に並べて一望したときに、「すごいな!」と感動するとともに、集まった様々な可能性は選定メンバーのみでなく、社内全体で感じてほしいと思いました。
ですので、今回集まったアイデアを社内で共有できる様にしました。最終的に選ばれなかったものを、眠らせてしまうのは勿体無いので、各々の社員が目を通して、実際のプロジェクトに活かせるアイデアを発掘してもらえる様にしています。300以上ものアイデアには全社員の熱意が集まっています。
堀田
SIwCoとして選出されたものは6つのアイデアですが、先ほど本田が言ったように、選から漏れたものも、実際のクライアント案件に使えるものがあれば、新たなプロジェクトの一部として利用する、そういった動きが出ています。ついこの間も関西で推進していたプロジェクトで、新入社員が考えたSIwCoのアイデアが採用されたと報告がありました。アイデアを出した社員も、別のプロジェクトに活かされて喜んでいます。
また、この後話をする初弾プロダクト「ディスタンスのれん」「和扇」については、意匠権の登録を進めています。「和扇」は既に登録査定を通過しており、本登録の準備が進んでいます。
『ディスタンスのれん』
ソーシャルディスタンスでも大切にしたい、人と人とのコミュニケーション

竹内
今回選ばれた“ディスタンスのれん”は、3案出した中の最後に出てきたアイデアです。僕、会社の帰りに立ち飲み寄って、知らんおっちゃんと喋るのが大好きなんです。
そこに視点を置いたらいろんなプランがどんどん出てきました。カウンターはこれぐらいの幅やろなぁ、コロナで今までと同じような飲み方やったらあかんな。ならついたてがいるなぁとか、ついたてが固い素材だったらイメージも固いし、暖簾みたいなものだったら、「ちょっとごめんよ」と、覗くこともできるなあ、とか。じゃあ暖簾はどうやって吊るす?天井からだと、どの店にでも使えへん。簡単にポン!と置けるものは?と考えていくと形のアイデアも出てきました。安定感だとか高さだとかバランスなど、イメージが降りてくるんです。アイデアを出すことに関してはスムーズにできたかな。
こだわったポイントはどんな店でも使いやすいように。基本ベースがあり、そこにオプションパーツを加えることで、印象が変わります。ベースは鉄ですが、焼き杉や竹などの素材をかぶせると表情がガラッと変わるんです。のれん部分も形や、素材を変えることでバリエーションが広がります。
残念だったのはこういった細かなパーツを変えていろいろなバリエーションができる点にあまり拘れなかった事。早く製品化する事を求められたので、そこまで時間がなかったんです。でも今回 SIwCoに選んでもらえたのは嬉しかったですね。今この製品は仙台の「うどん酒場 七右衛門」さんで使われています。仙台の方から「さすが船場さん!」という声を人づてに聞いてとても嬉しく思いました。直接感想が聞けたらもっと嬉しいですよね。(笑)
『和扇』
“おもいやり・おもてなしの心・なごみ”を表現出来たら
荒木
九州支店勤務なのですが、期間限定業務の為、1月から上京していました。ところがコロナの影響で前線後退し、九州で在宅勤務に逆戻り。
意気消沈した東京を目のあたりにし、連日の暗いニュースを見ながらもやもやと在宅勤務を進めていたそんな折、社長から「何か弊社も知恵を出さなければ、内装業界に携わって来た意味がない!」という旨のチャットが配信。九州でもクライアントが困っていらっしゃる状況も聞いていて、何かお力にならなければと、 SIwCoのアイデア出しを開始しました。
さて。どうしたものか?船場が作るのだから、ありきたりなものでは意味がない。オリンピック延期も決まり、撃沈・沈黙した日本が再度立ち直る為には、日本人の心が大切。困っている方々へのおもいやりの気持ちが、癒しやなごみとなって伝わるようなもの。コロナ終息後に再度日本を訪れる海外の方々に、おもてなしの心を感じてもらえるようなもの。そこから発想して、可変・持ち運び出来る、扇型のパーテーションのデザインに行きつきました。名称は、“話・輪・環・和”が生まれる日常が戻る事を願って、扇のモチーフに和の文字をつけた“和扇(わせん)”。“ことだま”の響きが一番しっくりきました。

荒木
アイデア採用の連絡を受けた時には、「あっちゃ~やっばーい!」と、実は素直に喜べませんでした。というかピンチ!パーテーションとして自立させるのが容易ではない事が、公募時よりわかっていたからです。
まずは作ってみるしかないなと、連日連夜、在宅勤務のベランダは「荒木商店ベランダ製作所」となり、ダイニングテーブルを占拠しモックアップモデルを作成。いつも苦楽を共にしていただいているディスプレイ業者の工場へ転がり込み、一緒に製作したものがグランスタ東京へ試験導入されました。
消毒液にも耐え、また光を通しながらも遮蔽する障子をイメージした障子紙風耐水塩ビシート製がオリジナルデザインですが、その折り方はかなり繊細で、作りも金額も伝統工芸品的に!(売れるんか?)障子紙風シートメーカーの方にも見ていただき、感銘・賞賛をいただきました。
最終的には障子紙風耐水塩ビシート製、別注印刷も出来る強化紙製、視線を遮蔽しない透明製もラインナップし、まるでアニメ・エヴァンゲリオンのように、スタディ・モックアップ・プロトタイプを経て、鶴や孔雀の翼のような『和扇3兄弟』が誕生しました。
松田
作ったはいいものの、これをどの様にクライアントさんに使っていただくか?を横木さんと考えていたところ、「動画を撮ろう!」と思いつきました。。
紙の取扱説明書を読むのは手間ですが、動画で使い方を見てもらった方が動く、たためる、という和扇の魅力をよりわかっていただけると思ったのです。横木さんや同じ部署の社員に協力・友情出演してもらいながら取扱動画を作成しました。コロナ禍で商品を持ってお客様に会いに行くということが難しくなったので営業ツールとして動画は便利です。併せて、パンフレットや商品に同梱する仕様説明書も作成しています。
荒木
他にも、実装をイメージした合成写真や、金額シミュレーション等、考えられる事は殆どやってみました。すると販売促進の大変さに改めて気づき、同時に世の中のモノづくりをしている方々へのリスペクトも生まれました。
横木
飲食店も宣言解除後当初は、8人がけのテーブルを4人のお客様で使っていました。間隔を開けると飲食店は客席数が売り上げに直結するので、要は半分しか売れないわけです。そこでパーテーションを使い空間を仕切ってあげることで客席数を8席は無理でも6席使えるようにする等、飛沫防止だけでなく客席効率の向上として使っていただきたい製品でした。
1番目は飛沫感染防止、2番目は客席効率座席数回復、3番目はお店演出役として、4番目はこれからアプローチしたいのですが、広告媒体として。この4つの役割をイメージしたのですが、広告媒体として活用するためのアプローチを今後どの様にして行くかは課題です。
松田
心斎橋OPA様より、販売促進も兼ねた話題作りの為に和扇の導入の引き合いのお話をいただきました。
クリスマスをイメージしたもので提案してほしいと言われたので、花を開いたデザインにしたら素敵だろうなと考えて、ポインセチアをイメージしてデザインしました。地下2階フードコートで“和扇”を採用していただいたのですが、その写真がバズりまして…!Twitterで2万リツイートされ、7.8万いいね!を頂いた中には、有名な議員さんも「素敵!」のコメントでリツイートをいただきました。
横木
デザインとカタチが一緒になって完成したのが“和扇”。2人のアイデアとデザインが合体したときに初めて想像以上の完成形が出来上がりました。
和扇は飲食店をイメージしていましたが、図書館のテーブルの遮へい板として使えないかとアイデアをいただきました。図書館は話す場所ではないので飛沫感染防止というより、隣との距離を取るために、また簡易的なブースを作るためのパーテーションとしての利用です。使う人が様々な使い道を考えてくれる自由度が今回の SIwCoで選ばれた両製品にはあります。
今回“ディスタンスのれん”と“和扇”を作るのに、アイデアを出した両名をはじめ、多くのスタッフが情熱を注ぎました。その中には、製品化するために奔走してくださった、協力企業の皆様の力もあります。みんなの想いがそれぞれの製品には込められています。
User Voice / お客様の声

以前はお客様の安心・安全のため大きく席間を空けて営業していましたが、ディスタンスのれんを設置し、必要以上に間隔を空ける必要がなくなったため機会ロスが減りました。 また、パーテーションがあることの安心感に加え、他にはない素敵なデザインで、お客様から「おしゃれだね」「雰囲気がいいね」とお褒めの言葉を頂きます。
太田奈々 様
株式会社ハミングバード・インターナショナル
うどん酒場七右衛門新伝馬町店 店長

ファッションビルのフードコートで若い女性も多くご利用いただいているため、デザイン性、機能性含め違和感なくご利用いただけると思い導入させて頂きました。ご利用いただいたお客様からは、パーソナルスペースが守られ、周囲を気にすることなくお食事ができるとお褒めのお言葉を頂いております。
心斎橋オーパ公式サイト
岡本悠亮 様
和扇導入店舗:心斎橋オーパ B2階 フードコート
株式会社OPA 心斎橋オーパ 営業企画グループ
【総括】株式会社船場 代表取締役社長 八嶋大輔より

当社グループには店舗デザインのアイデアを四六時中考えている社員が沢山います。昨年、未知のウイルス感染が拡大し不安が高まる中、「人々が安心して消費や娯楽などの経済活動を再開していくためにはどうしたらいいのか。今人類が抱える最大の課題に対して、何にもアイデアが提案できないなら店舗デザインを何十年もやってきた意味がない。これは船場の社会的使命でもある!」と呼びかけると上記の通り、出るわ出るわ。
今回はその中から「ディスタンスのれん」と「和扇」を商品化しました。アクリル板とは違う柔らかな雰囲気でプライバシー感と安心感をもたらし、コロナ後もお一人様需要や外国人旅行者に訴求できるのではないかと思っています。また実際にウイルスを除去するコーティングや照明なども開発しており、新しい時代の店づくりや改装のお役に立てております。








